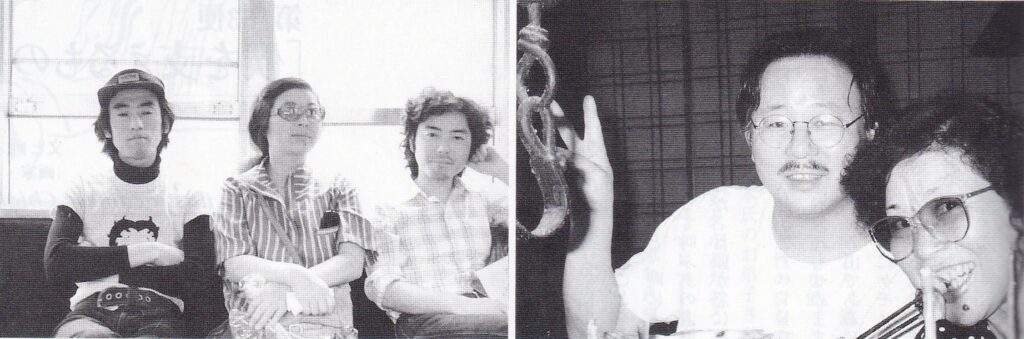<月刊パセオフラメンコ名作アーカイブ/2002年6月号)
【4】ゴールデン街の“息子たち”
文/菊地裕子
『ナナ』はフラメンコの居酒屋である。店にはいつもフラメンコの音楽が流れ、アーティストや愛好家が演奏を始めれば、それを喜びこそすれ、とがめる者はまず、いない。
しかし、客の誰もがフラメンコを目的に店に来ていたというわけではなかった。私が特に驚いたのは、何十年来の常連の中に、そう語る人が少なくなかったことだった。その中に、二十歳前後に『ナナ』の扉を開け、毎日のように通っていた人達がいた。"ミズキ〟、〝ババちゃん”、“タベちゃん"、"デカシン"、"チビシン"、"ムライちゃん"、"マッちゃん"、⋯⋯。 『ナナ』で仲間を得て、まるでそこが安住の地であるかのように居着いた彼ら。フラメンコが盛り上がると、そっと店の奥に身を寄せ、声を低くして語り合った。店がさらに混めば、"ナナさん"に「ちょっと回ってくるから」と言って、ほかの店をハシゴして戻ったりした。"ナナさん"が亡くなった後、『ナナ』の仮営業をしようと決めたのは、彼らフラメンコのアーティストでも愛好家でもない人々だ。一番若い〝ムライちゃん"でも40代後半、ほかはほとんどが50代である。
本業で責任ある仕事をしながら、営利目的でもなく店を一軒切り回していくなど、考えようによっては酔狂な話だ。そこまでして『ナナ』を存続させたいと思った彼らの真情に触れたくて、今でも『NANA』に顔を出す3人の常連("ミズキ"、"タべちゃん"、"ムライちゃん")にそれぞれ話を聞いた。
「『ナナ』の2階にはね、ヘルメットが10個ぐらい隠してあったんだよ」
"ミズキ"(本名・水木芳行)がいたずらっぽく言う。彼が『ナナ』に初めて行ったのは1966年、18歳の時。当時のゴールデン街には70年安保に反対する全共闘運動に身を投じた多くの学生たちがいた。"ミズキ"もその一 人で、ヘルメットは機動隊と衝突するデモの際の必需品だった。ゴールデン街の店には全共闘の人々が常連となっていたところがいくつかあり、派閥によって店が色分けされてい た。『ナナ』にも3つぐらいのグループが来ていたという。

「あの当時、東京の学生の3分の1ぐらいが全共闘だったんじゃないの。新宿騒乱事件の時には『ナナ』に避難したって話も聞いたよ」 60年代半ば、大学の学費値上げ反対運動から火がつき、全国に燃え広がった全共闘運動は、68年10月2日の国際反戦デーに頂点を迎えた。ベトナム戦争反対を唱える学生・市民が全国で統一行動を行ったこの日、新宿では、米軍のジェット燃料を積んだタンク列車の輸送を阻止しようと、2万人とも3万人ともい われる学生・市民が終結し、機動隊と激突。国電(現JR)が放火されるなどの混乱が生じ、政府は騒乱罪を適用して見物人を含む多くの市民を逮捕した。石畳をはがしての投石と催涙弾。ゲバ棒と警棒。現在の新宿からは想像もできないが「新宿市街戦」とも呼ばれたショッキングな出来事だった。
私自身は世代が違うが、全共闘世代の人々から「新宿」に対する格別の思い入れを聞かされたことは何度もあった。いわく、「反体制の闘争をしていた学生たちに優しい街だった」「自分に火の粉がふりかかるのも構わず、匿ってくれた」
新宿騒乱事件の時に学生たちを匿ったのは、『ナナ』だけではない。ゴールデン街にはそういう店がたくさんあった。学生たちに優しい街―――それはゴールデン街が、体制に与しない文化人やアバンギャルドな表現者たちを吸い寄せたことと通じるかもしれない。
新宿騒乱事件の前年の67年、ゴールデン街と通りを一本はさんで隣接する花園神社で、アングラ演劇の雄たる唐十郎率いる状況劇場が、初めての紅テント公演を行った(同年、寺山修司の演劇実験室・天井桟敷も旗揚げし、新宿でいくつかの公演を行った)。”ニーニョ" の話によれば、その頃の『ナナ』には、唐と共に状況劇場を設立した麿赤児(舞踏家/現・大駱駝館主宰)が来ていた。“ニーニョ" は彼らと「ハプニング」と称して街頭パフォーマンスをしたこともあったらしい。
「僕がギターでシギリージャを弾く。 その後ろに男が数人並んでいる。人が集まってくると、一斉に裸のお尻をまくるわけ(笑)」
学生運動が終息した後も、新宿はしばらく若者文化発信の中心的な存在でありつづけ、彼らの止まり木、あるいは隠れ家的存在だったゴールデン街もにぎわった。
就職をせず、今で言うフリーターのようなことをしていた“ミズキ"は、百円玉を数枚握り締めて『ナナ』に通ったという。
「水割りが百円だったんだよ。五百円もあれ ば一晩飲めたからね」
もっと経済状態が苦しい時は、月極めで“ナナさん"に飲ませてもらっていた。1ヵ月2万円の後払いで、週4日は開店から閉店まで、 どれだけ飲んでもいいという約束。1万5千円しか払えない“チビシン" (故人)は、週3日までと決まっていた。
「開店より前に店に行くんだよ。するとね、2階(“ナナさん”の住まい)に上げてくれて、ビールとつまみを作って出してくれる。それで一杯やってると、そのうち店が開いて、下に知り合いが来て『降りてこい』って言うわけ。『待ってろ、これ飲んだら、そっち行くから」って言って。『ナナ』は、我が家の居間って感じだったね」
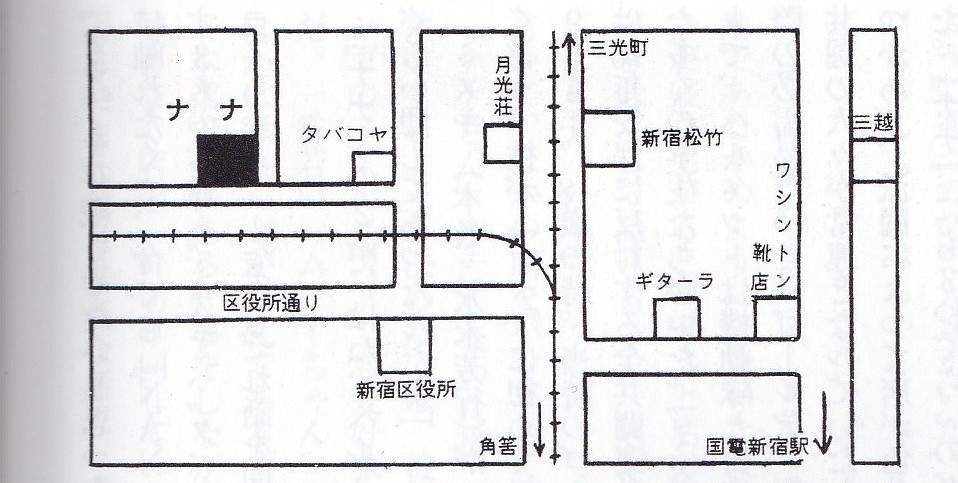
す。現在の“四季の道” はその名残りだ。
“ミズキ"より数年遅れて74年に『ナナ』の 扉を開けた"タべちゃん"こと喰始(たべ・はじめ/劇作家・演出家/劇団ワハハ本舗主宰)は、“ナナさん"と親しいメンバーを見て、その仲間に入りたかったという。
「オトナの遊びに思えたんですよ。行きつけの店で知らない人と酒飲んで話したり、そういう仲間と一緒に温泉やスキー旅行に行ったりするっていうのが」
“ミズキ"より1歳年上の“タべちゃん"は、19歳でテレビ番組「ゲバゲバ90分」の構成作家として名前が出て以降、売れっ子になっていた。『ナナ』に来た当時は24歳、レギュラー番組を減らしていた頃で、井上陽水のコンサートの演出をする以外は、週に1日も仕事をすれば十分な収入があるという状況だったという。
「週のうち6日ぐらい通った。つまり『ナナ』 が休みの日以外はほとんど毎日。新宿で映画見て、それから『ナナ』に行って、12時に 『ナナ』が閉店するから、その後はほかの店に行って朝までいて、始発で帰るんですよ。 15年ぐらいは、そんなことしてた」
いわゆる“ゴールデン街の常連たち"には、1軒で終わらず、数軒をハシゴして朝まで飲むというパターンがある。『ナナ』の斜向かいにある有名な『まえだ』(現在は閉店)は、2年前に亡くなった〝コミさん"こと田中小実昌(作家)が2階に寝ていた店だが、この〝コミさん"も一晩に10軒ばかりハシゴしていたという。『ナナ』にも顔を出していた。
店に居候する客、定職につかないアウトロー、自堕落な飲ん兵衛・・・・。ゴールデン街に は、特有の美学があったのかもしれない。「デカダンな雰囲気に憧れたんだよね。若い頃って、そういうのあるじゃない」と、"タベちゃん"は、はにかんだように笑った。
一方、さらに遅れて75年頃『ナナ』を訪れた "ムライちゃん"(本名・村井昭彦)は、名古屋から上京して青山学院大学の学生だった21歳から約8年間、毎日、あるいは1日おきに通った。きっかけは「海外への興味」。
「70年に大阪万博があって、 あれで世界に目が向いたみたいなところがあったんだよね」 スペインの関係ということで 『ナナ』に来たものの、フラメンコには格別興味はなかった。常連の中で最も若かった”ムライちゃん" は、年上の人たちの海外の話や専門分野の話を聞くのが面白かったらしい。
当時の彼は、大学対抗の麻雀の選手権で優勝した腕があり、プロの雀士になろうかと本気で考えていた。当然、麻雀の仲間はいたわけだが、『ナナ』の常連とは別だったという。"ミズキ"は『ナナ』を自分だけの隠れ家だと言ったが、〝ムライちゃん"にとってもそういう場所だったようだ。
「まるで自宅で飲むみたいな感じだからね。 リラックスして、仕事のことも忘れて」
その頃、『ナナ』の2階には、常連の一人だった山岳カメラマンの〝ババちゃん" 人)が居候をしていた。就職しなかった〝ムライちゃん"は〝ババちゃん"の助手を2年間やり、〝ナナさん"が2ヵ月ほどスペインに行って留守をした時には、店のカウンターに入って代役を務めた。そして24歳の時、バックパッカーとなって日本を脱出。約1年半をかけ、中国、パキスタン、トルコ、イギリス、ブラジル、アメリカ、ロンドン、フランス、スペイン、ポルトガル・・・・と回った。『ナナ』の古くからの常連で、ナナの生き字引と異名をとる〝フミコさん"(本名・松谷文子)に紹介状を書いてもらい、スペインではペペ島田の家に泊まったという。
帰国した〝ムライちゃん"は輸入雑貨の店を開こうと、2年ほど東京にとどまり、やがて名古屋で衣料関係の店を出すことになる。だが、仕入れで東京に来れば、必ず『ナナ』 に顔を出した。今は店を人に任せ、ワハハ本舗の制作として週末だけ名古屋に帰る。〝ナナさん"が亡くなって仮営業を始めた頃は、ワハハの若い役者たちと交替でカウンターにも入っていた。
”ナナさん"のことを、”ムライちゃん"は「お袋」と言い切る。”ミズキ"は「おっかちゃん」と言った。"夕べちゃん"にとっては「小さい時に生き別れた母親」だ。”ナナさん" の年齢については諸説あるので正確なところは分からないが、「本人が言った」として聞いた話では、フラメンコ居酒屋としてオープンした頃、すでに30歳は過ぎていた。母親というほどの年齢差はないが、要するに彼ら常連と”ナナさん"は、「家族みたいなもん」(”ミズキ")だったのだ。
”ナナさん"は若い人たちの面倒見が実に良かったと、いろんな人から聞いた。いわく、『ナナ』の閉店後に焼き肉屋や居酒屋で奢ってもらった、一緒に旅行に行って大盤振る舞いをしてもらった....。だが、家族とまで言う彼らは、もっと濃い付き合いをしていた。
たとえば、正月で店を閉めている時も、”ナナさん"は東京で一人で過ごす若い彼らのために、おせち料理と鍋を作って2階に呼んでくれたという。終電がなくて帰れなければ、2階に泊めてくれた(”ナナさん"は3階に寝起きしていた)。
そして、年に5、6回は、彼らを含めた仲の良い常連たちと海や山に旅行に行った。ヒマラヤにトレッキングに行ったこともある。20人以上の大所帯の時もあれば、3人だけの時もあった。〝ナナさん"にとって、旅行は大切なイベントだった。〝ナナさん"が亡くなった後、遺品の整理のために初めて2階に上がった”フミコさん"は、その余りの狭さに驚き、「この部屋に年中いたのかと思うと、〝ナナ"があんなに旅行に行きたがったわけがわかったような気がした」としみじみと話した。
それを聞いた 〝夕べちゃん"は、小さくうなずきながらもこう言った。
「〝ナナ"は貪欲でしたからね。外に出たがっ たんですよ。好奇心が旺盛で。名もない花と か、そういうのが好きだったんです」
私が『ナナ』に行き始めてしばらくして、"ナナさん"が倒れたことがあったが、体が良くなって久しぶりに旅行に行くという時、実にうれしそうだったのが忘れられない。「山に皆が連れて行ってくれるの!」と言っていた。「連れて行ってくれるの」と。たしかに、大きくなっても"息子たち" は、忙しい合間を縫って〝ナナさん"を旅行に誘い出していた。
バブルが最高潮になり始めた頃、ゴールデン街には地上げ屋が暗躍し、放火が頻繁にあった。櫛の歯が抜けるように、店が1軒、また1軒となくなった。"タベちゃん"は言う。「あの頃、客がほとんど来なくなったけど、僕らは、とにかく通いましたよ」
また、〝ナナさん〟が入院したり倒れたりするたびに、彼らは連絡をとって経済的な援助 もしたらしい。
「おっかちゃんが大変だから、おい、俺らでなんとかしようって」(〝ミズキ")
〝ミズキ"は、後年、軽井沢に自身の店を構え、新宿に出て来ることが少なくなっても、
半年極めと称して年2回、10万円ずつ〝ナナさん"に払い続けたという。
「俺だけじゃないと思うよ。皆、そうだったんじゃないかな」
私は彼らにそれぞれ気になっていたことを聞いた。どうして、〝ナナさん"が亡くなったあと、『ナナ』の仮営業をしようと思ったのかと。異口同音に彼らは言った。
『ナナ』には、昔、学生時代に常連で通っていて、今は地方で就職している人や、転勤でなかなか来れなくなった人がいる。そういう人は、たまに東京に出てきて『ナナ』に来るのを楽しみにしている。〝ナナさん"が亡くな ったことを知らない人もいる。彼らにゆっくりお別れをさせてあげたい、と。
ふと私は思った。それはまさしく、彼ら自身の心情ではないかと。
「だって、自分の家がなくなるようなもんだからね。年を取ればわかるよ。人生に、これ以上のものはないんだって」("ミズキ")
いま、『ナナ』はパコが営業する 『NANA』になった。それは彼らにとっては、昔の『ナナ』とは違う店だと彼らは言う。しかし、やはり異口同音に続けるのだ。
「でもね、パコには感謝してる。続けてくれ るだけで、ほんとにありがたいですよ」
取材中、パコが営業する 『NANA』のカウンターで、彼ら3人と飲む機会があった。その日は偶然、小森皓平とロス・パキートス の面々が何人かの愛好家とともに、歌とギターの宴を繰り広げていた。フラメンコが始まれば、静かに飲む。彼らの姿勢は、なんら変 わるところがない。しばらくして、ロス・パ キートスの土田正男がソロを弾いた時だったか、彼が某有名企業の社員であることをからかって、誰かが大声で企業名を野次った。とたんに"ミズキ〟が、ぽーんと言った。
「そんな肩書なんて、ここではなんにも関係 ないよっ」
"ナナさん"が言いそうなセリフだった。